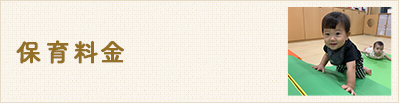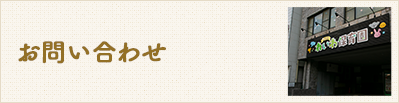園長だより令和7年4月号【本当の自立を目指して!】
本当の自立を目指して!
~ご入園・進級おめでとうございます~
園長 中村 洋志
令和7年度が始まりました。お子様のご入園・進級おめでとうございます。4月は新たなスタートの月であり、子どもたちの表情も普段以上に輝いて見えます。今目の前にいる一人一人の子どもたちが将来どんなに成長し、どんな生き方をしていくのか楽しみにするとともに、それぞれが自分らしい人生を生き抜いてほしいと願わずにはおられません。子育ては保育園だけでは出来ません。保護者や様々な方々との連携・協力の中で成長していきます。保護者の皆様方には、本年度も園の運営にご理解・ご協力をお願いいたします。
将来は一人の人間として自立し、豊かな人生を送ってほしいと願うのは、親や家族として当然の願いです。つい最近、ある書物(「生命尊重ニュース、2025年2月号」)で金剛寺住職の山本英照さんの文章を読んで、子育ての参考になりそうだと感じましたので、その一部を紹介いたします。「蜘蛛と言えば、某幼稚園の先生が『蜘蛛の巣に捕まっていた蝶々を逃がしてあげたら』と。幼稚園児が『蜘蛛が可哀相じゃないか。蝶々だってご飯が必要なんだよ』と。ハッとした。蝶々は『綺麗、可愛い、善者』と。人間は自分の勝手感覚で他者の決めつけを、と猛省を。子供教育と言えば、進学校の保護者会講演で『幼稚園時代から勉強以外は悪と、親が勝手に持論を押しつけ、レールを敷き、一流街道を歩まされた男性がいた。一流企業に入社したが、長続きがせず、45歳の現在、高学歴ニートに。5科目の出来るが人生の成功者と、勘違いして育てた親(大人)と、勘違いして育った子供。知識は学問から。その知識を活かす知恵は、経験から。経験なき知識持ちは、ただの『物知りさん』でしかない。子供時代に、当然経験させておかなきゃならん事を、親が悉く横取りして、何も出来ない人間を育成したのです。」という文章です。誠に耳の痛い話でありますが、ある面では核心を突いているような気がするのは、私だけでしょうか。
とは言っても子育てはなかなか根気のいる果てしない営みです。楽しみでもある反面、悩むことも多いのが現実ではないでしょうか。これが正解、これが最適という解がないからです。最終的には「自立した人間になること」を目指し、支援し続けることが私たち大人の役割ではないかと考えています。最近聞いた言葉で妙に納得した言葉があります。「自立とは、自分の周りにいかに多くの支える人がいるかである。」という言葉です。「自立」という意味は、一般的には「他の援助を受けず生きる」というイメージがありますが、「依存を増やす」という意味も含まれているという解釈もあります。一見相反する言葉のようにも聞こえますが、人間は一人だけでは生きていけない存在であるということだと思います。多くのサポートがあるということは、一人だけよりも安定して生きていけるということです。 それは、ただ単に数が多ければいいという話でもありません。少人数でもきちんと支えられて「自立」している人もたくさんいます。時には厳しく、時には優しく支えてくれる存在が人を勇気づけ、逞しく育んでくれます。それは、一番身近な親であったり、祖父母であったり、保育士や教師であったり、友人であったり、時にはまったくの他人であったりします。まさしくそのことが「出会い」の価値なのかもしれません。
保育園という様々な個性の子どもたちが一緒に過ごす中での経験は、 ある意味では「自立への過程を歩んでいる」ということかもしれません。すべての子どもたちが、お互いに支え合いながらも自分らしく輝いている姿が一番理想のような気がしています。それぞれが豊かな個性を発揮しながら大きく成長していけるような支援ができればと願っています。私たち職員も保護者の方々と連携しながら、一人一人の成長に寄与できるように日々の取組を進めてまいります。
ある意味では「自立への過程を歩んでいる」ということかもしれません。すべての子どもたちが、お互いに支え合いながらも自分らしく輝いている姿が一番理想のような気がしています。それぞれが豊かな個性を発揮しながら大きく成長していけるような支援ができればと願っています。私たち職員も保護者の方々と連携しながら、一人一人の成長に寄与できるように日々の取組を進めてまいります。