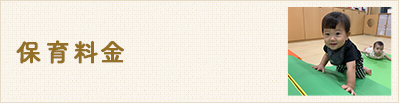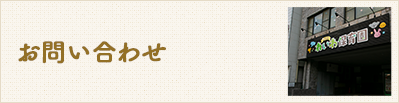園長だより令和7年10月号【子どもの発達の証!】
子どもの発達の証!
~子どもの嘘は、成長の一つ?~
園長 中村 洋志
暦の上では秋ですが、長期の天気予報でも当分の間、暑さは続くとのことのようです。安心して戸外で遊べるような状況になればと願っています。子どもたちは、急に大人になるのではなく、様々な経験を通して心身共に徐々に成長していきます。しかも、個々人によってそのスピードには違いがあります。私たち大人は、自分にも子ども時代があったことを思い出しながら、その子なりの成長を温かく、時には厳しく見守っていく必要があるのではないでしょうか。
最近読んだ書物で、気になる文章に出会いました。白梅学園大学子ども学部子ども心理学科佐久間路子教授がある動画を見ていての感想を述べたものです。「バナナを食べたくて、目に手を当てて『えーん、えーん』と言っているのですが、涙は流れていません。バナナをもらえたら、すっと泣くふりをやめて、夢中に食べていました。このような嘘泣き(例えばミルクが欲しくて泣いているような大声を出す)は、早くは8か月から見られるとの報告もあります。さてこの子は『嘘』をついているいるのでしょうか。本当に泣いているのではなく、泣いている『ふり』をしていると考えられます。」という文章です。「ふり」はあくまでも「まね」であり、本当のことではなく嘘の世界です。嘘泣きをして親を意図的に嘘泣きをしているのではなく、過去の経験から、泣けば欲しいものがもらえるということを学んだ結果のことだと考えられます。その子なりに泣くことが効果的なコミュニケーションツールの一つとして自然と身に付けたものだと考えられます
相手を欺こうとする意図の理解は幼児期後半(5~6歳頃)に発達するそうです。 幼児期後半になると、とっさに嘘をついて、自分がしたことから逃れようとする行為が見られることもあります。嘘が言えるようになったという子どもの成長を見守りつつ、嘘がばれた後の子どもに対してどう対応するかは、難しい判断になりますが、ただ一方的に叱るだけだはなく、そこに至るまでの子どもの心情にも寄り添いながら冷静に対応していくことが大切ではないかと考えています。子どもの年齢や心身の発達の状況を把握しながら、対応しないと一方的な叱り手に
幼児期後半になると、とっさに嘘をついて、自分がしたことから逃れようとする行為が見られることもあります。嘘が言えるようになったという子どもの成長を見守りつつ、嘘がばれた後の子どもに対してどう対応するかは、難しい判断になりますが、ただ一方的に叱るだけだはなく、そこに至るまでの子どもの心情にも寄り添いながら冷静に対応していくことが大切ではないかと考えています。子どもの年齢や心身の発達の状況を把握しながら、対応しないと一方的な叱り手に
なってしまいます。
子どもたち一人一人の深層心理を理解することは至極難しいことですが、子どもの心情に寄り添うことはできます。子どもの行動には必ず理由があります。子どもに寄り添うことは、子どもを甘やかすことではありません。大人の正論を押し付けるだけではなく、子どもの言動の背景にあることにも思いをはせ、周りの方々にも相談したり、客観的な情報を得たりしながら冷静に対応して欲しいと願うばかりです。私にも幼い頃、当時は珍しいアメリカの親戚から送られてきたチョコレートを棚から取り出し口の周りをチョコ色にして、母から「チョコを食べたでしょう」と言われ、「食べてないよ」と見え透いた嘘を言うなど、「これからは絶対に嘘をつきません」と何回も約束させられた、振り返りたくない、笑えない苦い過去があります。